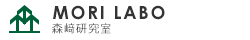研究代表者
氏名:森﨑 巧一(京都経済短期大学経営情報学科 教授)
保有学位:博士(デザイン学)(筑波大学)
研究分野:デザイン学、感性情報学、ウェブ情報学、サービス情報学、教育工学、ヒューマンインタフェース、インタラクション
研究キーワード:デザイン学、印象評価、情報デザイン、感性心理学、感性工学、データサイエンス、情報可視化、鑑賞支援、鑑賞支援に係る情報分析と技術開発、文化、芸術、ポップカルチャー、サブカルチャー、インタラクティブアート、メディアアート、コンピュータミュージック、DTM、3Dプリンター、ドローン、生成AI、漫画、アニメ、イラストなど
自己紹介
私の両親は関西で画廊を営んでいました。私は画商としての英才教育を受けたというわけではありませんが、商業的に扱われる芸術の世界を垣間見て育ちました。ニューヨークやロンドンで開催されるサザビーズ(Sotheby's)やクリスティーズ(Christie's)の絵画のオークションに参加したり、東京や大阪、名古屋などで開催される美術品の交換会にも何度か参加させてもらいました。画廊の息子として生まれなければ、このような世界をみることはできなかったかもしれず、大変貴重な経験をしました。しかし、オークション会社の作品紹介などで大学の教授の名があったりすると、研究の世界に魅力を感じ、ビジネスとして芸術を扱うよりも、研究者として芸術に関わってみたいと思うようになりました。また、1990年代初めの頃に約1年英国に留学しましたが、その際にロンドンの美術館や博物館にあった作品情報の提示装置に影響を受け、コンピュータで芸術の鑑賞を支援する研究をしたいと思い、芸術に関係する研究の世界へ入門することに決めましました。1990年代半ば頃、博物館学芸員資格を取りながら美術と鑑賞についての個人研究を開始し、当時はあまりメジャーではなかった鑑賞支援という言葉も、”一般鑑賞者に向けての情報提供をサポートすること”という独自の解釈で使用しはじめ、美術史や芸術作品などについての専門的な情報を分かりやすく提供するWebサイトを作成していました。当時はWindows OSやインターネットも普及しはじめたばかりの頃で、時期尚早だったのか、私の考えるコンピュータを使って芸術の鑑賞を支援する方法の研究は、美術館・博物館の学芸員はおろか、ほとんどの大学でも重要性をあまり理解してもらえませんでした。
実際、鑑賞支援の研究と一口に言っても、芸術の世界は大変広くて深いものです。はじめはどこから手を付ければ良いのか途方に暮れましたが、両親の昔の知人で画家だった筑波大学の教授の紹介により、美術鑑賞をテーマに研究している同大学の研究室で修行させて頂くことになりました。その後、大学院で正式に研究をすることになりました。最初は美術鑑賞支援をテーマに研究をするものと思っていましたが、その研究室は本来デザイン(プロダクトデザイン)を専門とするところだったため、研究内容は美術鑑賞からデザインの研究にシフトしていき、デザイナーとしての基礎が全く無かった私にとっては何もかもが未知で、非常に苦しい環境でした。しかし、デザイン学分野の研究に関わることで、印象評価(感性評価)という私にとってはかけがえのない研究手法を学ぶことができました。鑑賞行為は、人の感性が深く関わっています。美術鑑賞に感性研究の手法を応用することで、鑑賞支援に関する何らかの有効な手がかりが見えてくるかもしれません。そこで、造形の印象評価の研究を極めていくことにしました。大学院の博論は立体造形の触覚鑑賞をテーマにしながら印象評価法をも取り入れてみたのですが、興味のある両方の研究内容を融合させた集大成となり、個人的には大変満足しています。この研究を行うにあたり、工学や心理学、芸術学、教育学などの先生方や学生の皆様、興味を持って頂いた企業の方々にも大変感謝している次第です。大学院を出た後も分野を横断する研究(いわゆる領域横断研究)は、これまで何度も行ってきましたが、そのような研究を通して色んな人との出会いがあり、大学だけでなく、研究所や美術館・博物館や企業の方々ともたくさんの交流ができました。そして、情報学や工学、心理学、統計学などの手法を援用しながら、芸術やデザインの分野に貢献できる感性研究を追求し、さらには、芸術やデザインの分野にとどまらず、むしろ他分野の方々とも積極的に交流しながら横断的研究を推進してきました。学部時代に情報処理やプログラミングなどを学んでいたことも役立っており、情報学とデザイン学を行き来しながら情報デザイン教育に携わり、今日に至っております。
1990年代後半から本格的に始まった私の研究は、現在でも芸術やデザインを対象に、人の印象評価を分析する感性研究を中心に取り組んでおり、この研究分野については20年以上携わってきました。感性研究では、統計データ解析の手法やITの技術を使用し、数値データの解析結果をもとに、芸術やデザインに対する感性的な特徴を抽出したり、新たな価値を見出せるポイントを発見したりするので、今注目されているデータサイエンスに近接する研究分野であるといえます。ちなみに最近は、調査で扱う印象語を多言語(英語、フランス語、中国語など)にしたり、地域特有の印象語(例えば京言葉など)を用いたりして、印象評価法を文化研究の分野にも拡張して扱っています。印象評価法を使用した感性研究だけでなく、初学者には扱いづらい印象評価法をサポートする教材ツールの開発、画廊での経験や長年の鑑賞経験を生かした美術鑑賞を支援する研究、情報デザイン教育の知見や経験を生かしたメディアアートの研究、漫画やアニメ、イラスト、音楽などのポップカルチャーに関する研究なども行っています。情報デザイン教育では、コンピュータグラフィックスやWebデザイン、写真や動画の編集のようなオーソドックなものだけでなく、ドローンや3Dプリンター、生成AI、デジタルサウンドなど学生が興味を持つテーマや先進技術も積極的に取り入れながら教育研究を行っています。
研究協力者(現在遂行中の研究)
小路 真木子(京都経済短期大学経営情報学科 教授)